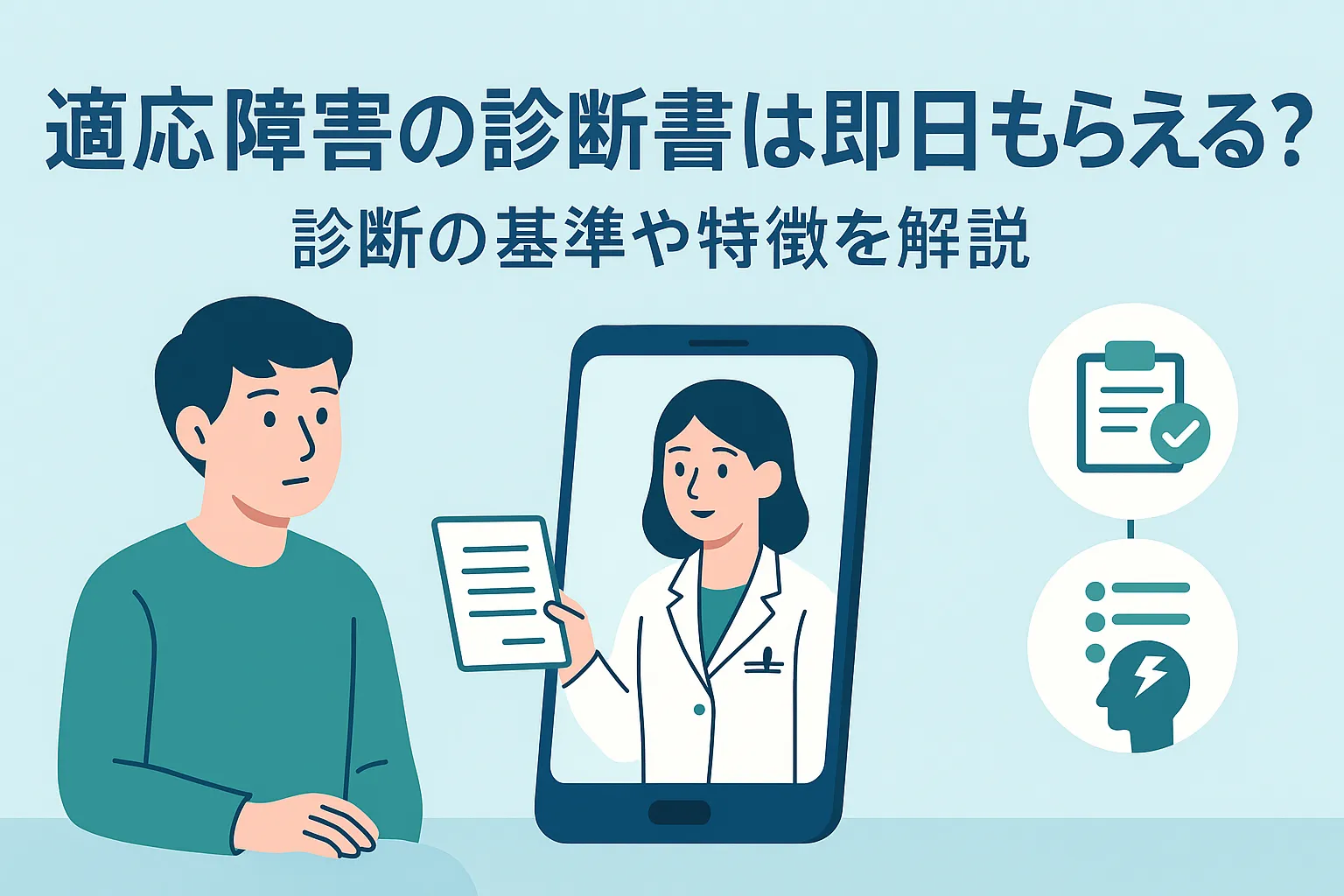「適応障害と診断されたけど、医師から診断書をもらえない」
「会社や学校に提出するために必要なのに、どうして発行してくれないの?」
こんな不安や困惑を抱えていませんか?
診断書は単なる病名の証明ではなく、あなたの心身の状態や生活・社会での困難を医師が客観的に示す重要な書類です。
これがあることで休職手続きや傷病手当の申請などがスムーズに進みます。
しかし、医師がすぐに診断書を発行しないことには、いくつかの理由が存在します。
本記事では「適応障害で診断書がもらえないケース」に焦点をあて、以下のポイントをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、診断書がもらえない状況への理解が深まり、医師との建設的なコミュニケーションのヒントや、今後の具体的な行動につながる情報を得られるでしょう。
適応障害と向き合い、より良い方向へ進むための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

| メニュー | 詳細 |
|---|---|
| 初診料 | 3,850円〜 |
| 再診料 | 2,980円〜 |
| 診断書発行 | 〇 当日相談可 |
| 診察時間 | 11:00〜23:00 曜日によって異なる |
| 当日予約 | 〇 当日診察も可 |
- 当日予約から診察も可能!
- 医師の診察のもと診断書即日発行
- LINEから24時間予約対応
- 診断書〜傷病手当金の相談もOK
「メンクリ」は、LINEから24時間いつでも予約可能!オンライン心療内科だから通院ゼロ、診察〜診断書発行まで自宅で完結します。
診察後には即日診断書を発行(※)し、取得後の休職手続きや傷病手当金申請まで専任スタッフが丁寧にサポートするので安心。
\今すぐ医師に相談できる/
※医師が必要と診察した場合
適応障害と診断・診察される内容とは
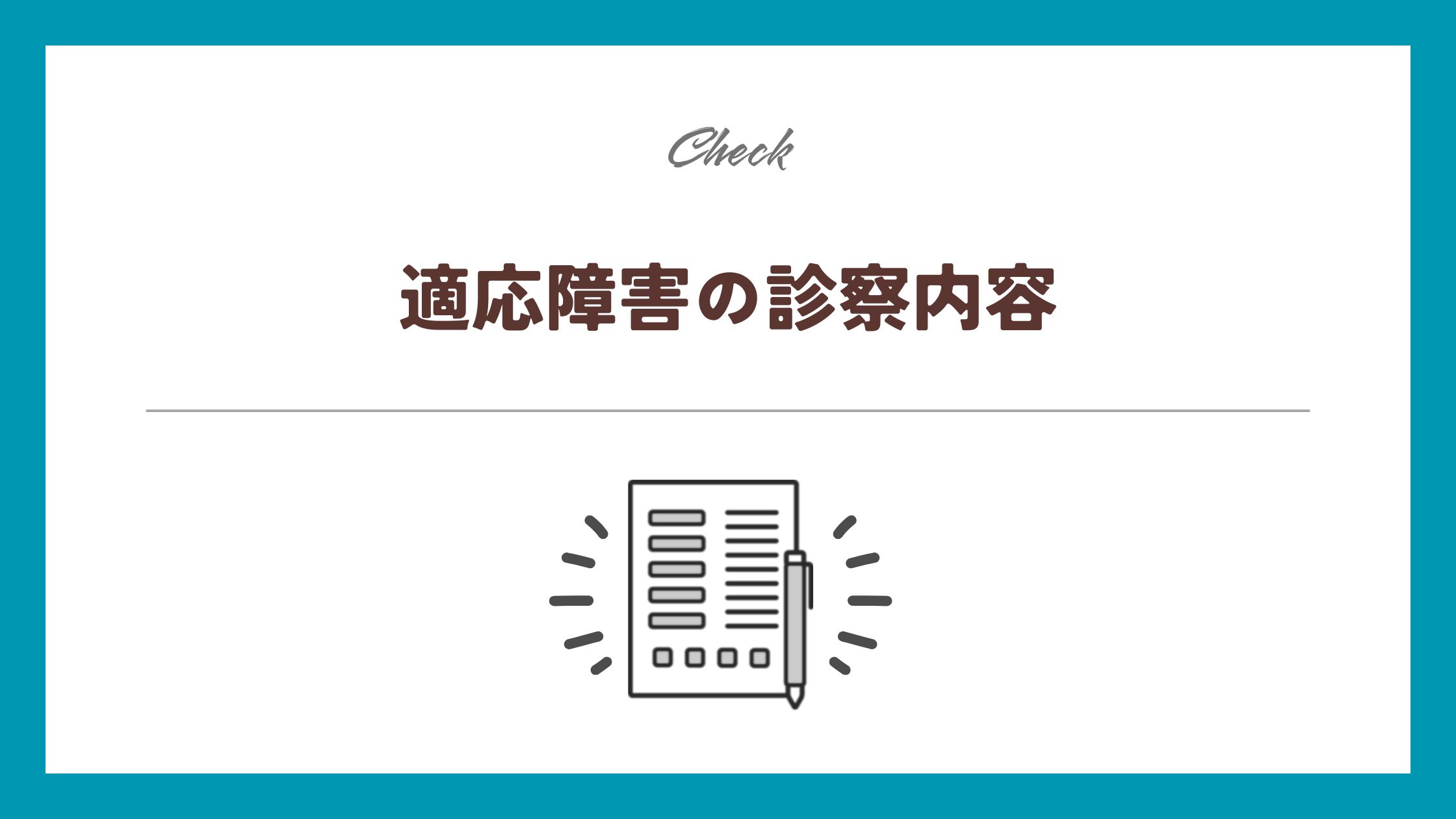
「適応障害と診断されるとき、どんなことを見られるのか知りたい」
「診断書にどんな意味があるのか、どう活用されるのか気になる」
そんな疑問を感じる方のために、診断・診断書の内容や基準についてわかりやすく解説します。
適応障害の診断書がもらえない理由と対策はこちら
適応障害の診断書は、医師が「現在の心身の不調が適応障害に由来する」と医学的に判断し、その所見・治療方針・必要な配慮を記した公的な証明書です。
この診断書は、患者が社会生活を送る上で直面する困難(仕事に行けない、集中できないなど)が、病気(適応障害)に起因するものであることを、第三者(会社、学校、行政機関など)に示す目的で使用されます。
適応障害の診断基準
適応障害は、特定のストレス因子(例:職場環境の変化、人間関係の問題、失業、家族との別離など)に反応して生じる精神的・身体的な症状によって特徴づけられる精神疾患です。
診断にあたっては、国際的な診断基準であるDSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)やICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)が参考にされます。
適応障害の診断基準の主なポイントは以下の通りです。
- 明確なストレスの原因がある
- ストレス反応で生活に支障が出ている
- 心と体にさまざまな症状があらわれる
- ストレスがなくなると回復していく
- 他の病気や自然な悲しみとは違う
明確なストレスの原因がある
適応障害は、原因がよく分からない心の病気とは違い、何かしらのストレスの原因がはっきりしているのが特徴です。
例えば、上司からの厳しい叱責、部署異動や転職、家族の介護、離婚など、本人にとって大きな負担になる出来事が発症の引き金となります。
特に、発症の3か月以内にその出来事があったかどうかが判断されます。
ストレス反応で生活に支障が出ている
同じ出来事に対して、人によって感じ方や耐えられる範囲は異なります。
適応障害と診断されるのは、その反応が「通常よりも強く、仕事や日常生活に支障が出るほど」である場合です。
例えば、仕事に行けなくなる、布団から出られない、人と話すのが怖くなる、といった状態が当てはまります。
心と体にさまざまな症状があらわれる
適応障害では、気分が落ち込む、不安が強くなる、イライラしやすいなどの心の症状に加え、不眠や食欲不振、強い疲労感といった体の不調があらわれることもあります。
また、無断欠勤や遅刻、家に引きこもるなどの行動の変化が目立つ人もいます。
ストレスがなくなると回復していく
適応障害は、うつ病のように長期間続く病気とは異なり、ストレスの原因が解消されると自然に回復していくのが特徴です。
通常は6か月以内に改善していきますが、ストレスが長引いている場合は症状も長引くことがあります。
他の病気や自然な悲しみとは違う
同じように落ち込む症状が出る病気として、うつ病や不安障害がありますが、適応障害はそれらとは区別されます。
また、身近な人を亡くしたときに感じる「正常な悲しみ」とも異なるとされています。
医師はこれらの基準に基づき、患者の訴え、面談での様子、これまでの経過などを総合的に判断して診断を行います。
診断が確定するまでには、数回の診察や経過観察が必要となる場合もあります。
ちなみに、「診断書が出ないのはなぜ?」と気になる方もいるかもしれません。その理由は後半で触れますので、ぜひ読み進めてください。
適応障害の診断書の効力や必要な場面

適応障害の診断書は、様々な場面でその効力を発揮します。代表的な場面は以下の通りです。
- 休職・休学
- 勤務形態の変更・配慮依頼
- 傷病手当金の申請
- 障害年金の申請
- 失業保険の申請
- 転職活動
- 裁判や調停
休職・休学
症状のために仕事や学業を継続することが困難な場合、診断書を会社や学校に提出することで、療養のための休職・休学が認められる手続きの根拠となります。期間や復帰の見込みについても医師が記載します。
勤務形態の変更・配慮依頼
症状が重くない場合でも、時短勤務、部署異動、業務内容の変更、テレワーク導入など、働き方に関する会社への配慮を求める際に診断書を提出することがあります。
傷病手当金の申請
健康保険組合から支給される傷病手当金は、病気や怪我で働くことができず給与が得られない場合に、生活保障として支給されるものです。申請には医師の診断書が必要です。
障害年金の申請
適応障害の症状が長期にわたり、日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害年金の申請が可能となることがあります。申請には診断書を含む複数の書類が必要です。
失業保険の申請
離職理由が適応障害による体調不良である場合、自己都合退職ではなく特定理由離職者として扱われることで、失業保険の受給に関して有利になることがあります。この場合も医師の診断書が証明となります。
転職活動
次の職場で自身の健康状態について説明したり、必要な配慮(残業を控えるなど)を求める際に、診断書を提出することがあります。
裁判や調停
精神状態が関連する法的手続きにおいて、医師の診断書が証拠として提出されることがあります。
このように、診断書は単なる「病気の証明」にとどまらず、患者が療養に専念したり、社会生活上の困難を軽減したり、適切な公的支援を受けるために不可欠な役割を果たします。
診断書の効力と会社での取り扱い
診断書は、医師という国家資格を持つ専門家が、医学的な見地から患者の状態を証明する書類です。
そのため、会社や各種機関は原則として診断書の内容を尊重します。
- 診断書の内容がそのまま認められるとは限らない
- 休職や復職の最終判断は会社側の規定や産業医の意見が影響することも
- 診断書は個人情報。無断で第三者に開示されることはない
会社に診断書を提出すると、記載内容(病名・療養期間・必要な配慮)をもとに、休職手続きや配置転換、業務内容の見直しなどが検討されます。
そのため、診断書に「〇ヶ月の休職が必要」と書かれていても、会社の就業規則によって期間が調整されたり、休職が認められない場合もあります。
復職の際も、診断書だけで決まるわけではなく、産業医との面談や試し出勤など、会社の判断や手続きが必要になるのが一般的です。
診断書はあくまで医師による医学的な意見であり、最終的な決定権は会社にあります。
また、診断書には重要な個人情報が含まれるため、本人の同意なしに第三者へ開示することはできず、取り扱いには慎重さが求められます。
適応障害の診断書がもらえないのはなぜ?主な理由

適応障害の診断書が欲しいのに、医師から「今は出せません」「もう少し経過を見ましょう」と言われ、戸惑う人は少なくありません。
診断書がもらえない理由には、医師側の事情だけでなく、患者側の伝え方や状況も影響しています。
ここまでで診断書の役割やもらい方を解説しましたが、この章では、診断書がもらえない理由と、そのときの対応方法を詳しくお伝えします。
- 診断基準を満たしていない
- 診断確定に時間が必要
- 医師の専門外や判断が難しい
- 通院状況が不安定で状態把握ができない
- 患者側の症状や困り事が伝わっていない
診断書がもらえないケース1
診断基準に達していない・症状が不明確である場合
適応障害は、ストレス因によって引き起こされる様々な精神的・身体的症状を伴いますが、その症状が医学的に診断基準を満たすレベルであるか、あるいは他の疾患の可能性はないかを慎重に見極める必要があります。
- なんとなく元気が出ない
- 眠れない日がある など
また、症状が一時的で、受診時には落ち着いている場合なども同様です。
医師は患者の語りだけでなく、表情、言動、思考内容、生活への影響度などを総合的に観察し、診断の根拠を探します。
症状の訴えが抽象的であったり、診察ごとに内容に一貫性がなかったりすると、診断が難航し、診断書の発行が見送られることがあります。
診断書をもらうためには、自分の状態を具体的に伝えるのが重要です。
>>医師に自分の状態を適切に伝えるポイントが知りたい方はこちら
診断書がもらえないケース2
診断確定に経過観察期間が必要な場合
適応障害の診断は、単一の診察だけで確定するのが難しい場合があります。
特に発症から日が浅い場合や症状が軽い場合は、一時的なストレス反応かどうか見極めるため、数回の診察を重ねることがあります。
医師は、患者の現在の状態だけでなく、今後の症状の推移を予測し、診断と治療方針を決定します。
安易に診断書を出すことで、不利益(転職時に不利になる、誤った治療につながる)になる可能性も医師は考えています。
特に、初めての受診や、症状が軽微にみえる場合には、「まずは1~2週間後にまた受診して様子を見ましょう」といった形で、診断書の発行が保留されることがあります。
診断書がもらえないケース3
医師の専門外である、または判断が難しい場合
適応障害は精神科や心療内科で主に扱われる疾患ですが、内科やかかりつけ医などに最初に相談するケースも少なくありません。
内科やかかりつけ医などの一般科の医師は、精神疾患の診断に慣れていないため、判断がつきづらいことがあります。
また、患者が複数の疾患を抱えている場合や、複雑な家庭・職場環境の問題が絡んでいる場合なども、診断や治療方針の判断が難しくなることがあります。
医師がより専門的な評価が必要だと判断した場合は、診断書の発行を控えるか、精神科医や心療内科医への紹介を勧められることがあります。
診断書がもらえないケース4
患者の通院状況に問題がある場合(自己中断など)
診断書は、患者の状態を継続的に観察したうえで発行するのが基本です。
無断キャンセルや自己判断による中断があると、医師は患者の正確な状態を把握できず、「まだ診断書を出せる状況ではない」と判断する場合があります。
診断書には「〇ヶ月間の休職が必要」といった具体的な期間や、「復職にあたっては〇〇のような配慮が必要」といった意見を記載する必要があります。
医師は、診断書を出す前に「この先どのくらいで回復できそうか」や「今どのくらい生活や仕事に支障が出ているのか」を、できるだけ正確に判断する必要があります。
不安定な通院状況は、医師がこれらの判断を下す上での信頼性を損ない、「診断書を作成できるほど、あなたの状況を把握できていません」という判断につながる可能性があります。
診断書がもらえないケース5
患者側のコミュニケーション不足も影響する場合
診断書の発行には、医師だけでなく、患者側の準備や伝え方も大切です。
患者側のコミュニケーション不足が、診断書の発行を妨げる要因となることもあります。
症状や困り事を具体的に伝えられていない
漠然と「調子が悪い」と伝えるだけでは、医師が重症度や生活への影響を判断できません。
以下のように具体的にメモしておくのがおすすめです。
- どんな症状があるか
例)朝起きられない/涙が止まらない - いつから始まったか
例)3ヶ月前に異動してから - どんな場面で強まるか
例)朝の通勤時/会議中 - 頻度・強さはどのくらいか
例)毎日/週に数回 - 生活でどんな支障があるか
例)遅刻が増えた/家事が手につかない
このように、症状を具体的なエピソードや頻度、強度、それが引き起こす生活への影響を交えて伝えることで、医師はあなたの状態をより正確に理解しやすくなります。
診察前にメモにまとめておくのも有効です。
診断書の利用目的や提出先が不明確である
診断書は、その利用目的や提出先によって記載内容が異なります。
例えば、傷病手当金申請用の診断書と、会社に提出する休職願い用の診断書では、様式や求められる記載事項が異なる場合があります。
患者が診断書が必要な理由や、提出先を医師に明確に伝えないと、医師はどのような診断書を作成すれば良いのか判断できません。
また、診断書が必要な緊急性についても伝えないと、医師は発行の優先順位を判断できず、結果として発行が遅れたり、「目的が不明確なため発行できない」と判断されたりすることがあります。
「とにかく診断書が欲しい」という気持ちだけが先行し、その後の手続きや自身の希望について医師に相談しないことも、診断書発行のプロセスを複雑にする可能性があります。
診断書がもらえない理由は、医師だけでなく患者側の伝え方が不十分である場合もあります。
| 「医師側」の理由 |
|---|
|
| 「患者側」の理由 |
|---|
|
診断書がもらえない理由を知ることで、どのように医師に伝えればよいか、何を準備すべきかが見えてきます。
次の章では、診断書をもらうために患者側ができる具体的なポイントを解説しています。
今すぐ実践できるコツを知って、よりスムーズに休職や申請が進むよう準備しましょう。
もしも今すぐ誰かに相談したい、専門医を探したい場合は、オンライン心療内科『メンクリ』もご活用してください。
一人で悩まず、専門家に相談することが回復への第一歩です。
適応障害の診断書をもらうために医師に伝えるべきポイント
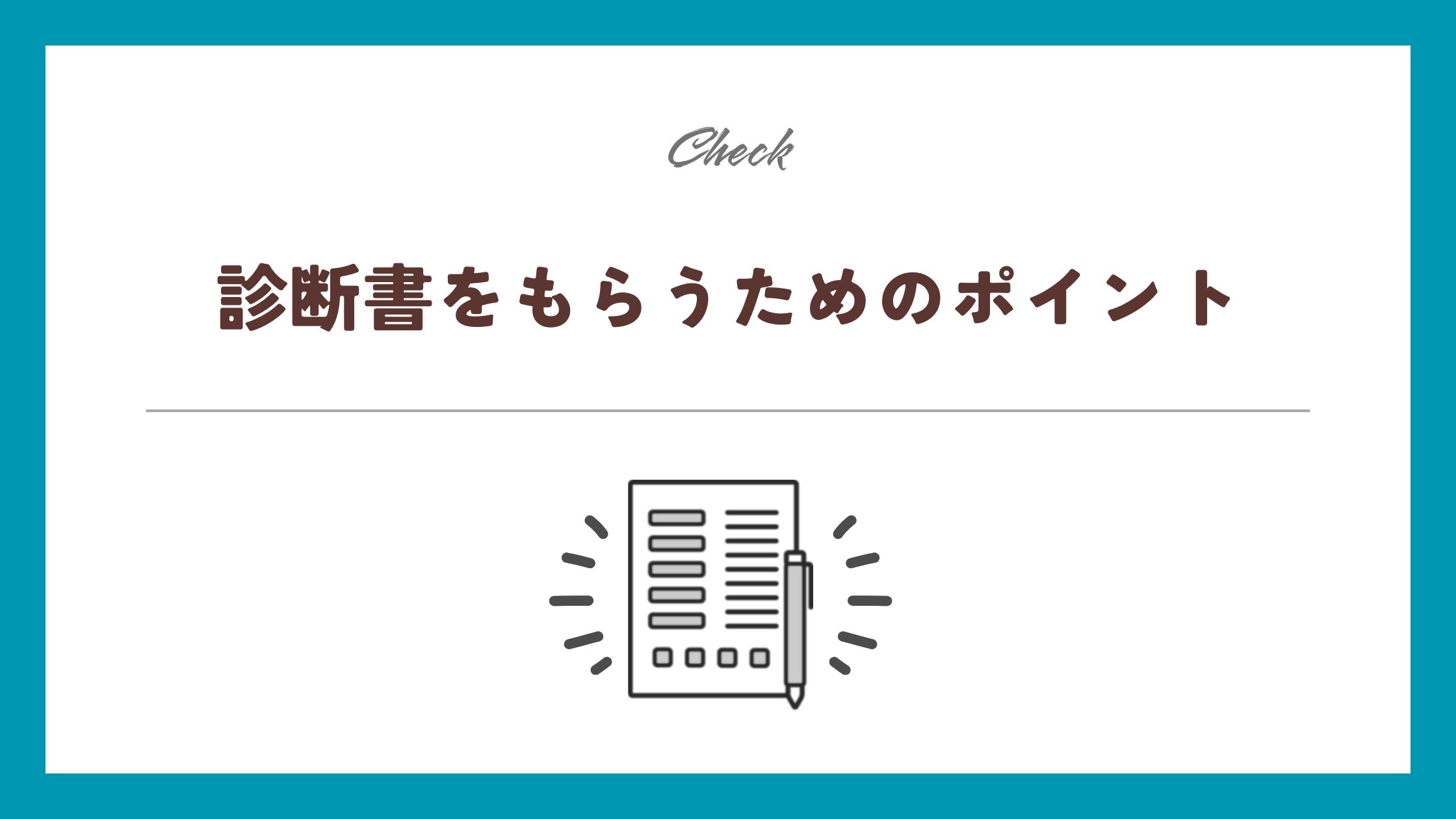
適応障害の診断書をスムーズに発行してもらうには、医師とのコミュニケーションがカギ。
限られた診察時間で、あなたの状況を的確に伝えるためのポイントを分かりやすくまとめました。
- 今の症状を具体的に整理する
- 症状が日常生活や仕事にどう影響しているか伝える
- 診断書が必要な理由や提出先を明確に伝える
- 症状が始まった時期ときっかけ(ストレス要因)を伝える
1.今の症状を具体的に整理する
まず、現在ご自身がどのような症状に悩まされているのかを具体的に整理しましょう。
症状を「つらい」「しんどい」だけで終わらせず、どんな形で現れているかを具体的に伝えることが大切です。
- 精神症状
気分の落ち込み/強い不安感/イライラ/集中力低下/涙もろさ/孤立感 など - 身体症状
不眠/食欲不振・過食/動悸/頭痛/倦怠感 など
これらの症状について、「いつから」「どのような時に」「どのくらいの頻度・強度で」現れるのかを具体的に説明できるように準備しておきましょう。
診察前にメモに書き出しておくと、伝え漏れを防ぐことができます。
2.症状が日常生活や仕事にどう影響しているか伝える
症状そのものだけでなく、その症状が原因で、あなたの日常生活や仕事(学業、社会生活)にどのような支障が出ているのかを具体的に伝えることが、診断書作成において非常に重要です。
医師は、症状がどの程度機能障害を引き起こしているかを判断し、診断書に記載する内容(例:就労困難、〇〇のような配慮が必要)を決定します。
- 仕事・学業への影響
遅刻や欠勤が増えた/満員電車で動悸がする/会議で発言できない/判断が鈍る など - 日常生活への影響例
家事ができない/外出が怖い/食事や入浴がおっくうになる/友人と会えない など
単に「仕事に行けません」と言うのではなく、「朝起きると動悸がして体が動かず、午前中は布団から出られず、結果的に遅刻・欠勤が増えています」といったように、具体的な状況を伝えるようにしましょう。
3.診断書が必要な理由や提出先を明確に伝える
なぜ診断書が必要なのか、その目的と提出先を医師に明確に伝えましょう。
- 会社に提出して休職したい
- 傷病手当金を申請したい
- 学校に提出して休学したい
- 今の部署から異動したいので会社に配慮をお願いしたい など
診断書の利用目的を伝えることで、医師は適切な様式の診断書を作成したり、必要な記載事項(例:病名、療養期間、就労の可否、必要な配慮など)を漏れなく記載したりすることができます。
また、期限がある場合は早めに伝えることも大切です。
4.症状が始まった時期ときっかけ(ストレス要因)を伝える
適応障害は特定のストレス因によって引き起こされます。
診断のためには、症状が出始めた時期と、そのきっかけとなった出来事(ストレス因)を明確に伝えることが重要です。
- 〇ヶ月前から
- 〇〇の部署に異動してから
- △△という人間関係の問題が起きてから
- 大切な□□を失ってから など
複数のストレス因が考えられる場合は、特に影響が大きいと思われるものや、最近の変化について詳しく説明しましょう。
ストレス因が明確で、それが取り除かれると症状が改善する傾向があるという点も、適応障害の診断において重要なポイントです。
ストレス因について具体的に語ることで、医師はあなたの症状が適応障害によるものである可能性をより強く考慮することができます。
- 現在の具体的な症状(精神・身体)
- 症状がいつ・どんな状況で出るか
- 症状が生活や仕事にどう影響しているかの具体的なエピソード
- 診断書の必要な理由と提出先
- 症状の開始時期ときっかけ(ストレス因)
- (あれば)診断書の提出期限
これらを整理して診察時に伝えることで、医師にあなたの状態が正しく伝わり、診断書の発行がスムーズに進みます。遠慮せず、正直に伝えましょう。
一人で悩まず、専門医に相談することで早期に診断書を取得しやすくなります。オンライン診療ならご自宅から気軽に相談できます。
『オンライン診療』という選択肢も◎
「対面で話すのが不安」「忙しくて病院に行けない」という方には、オンライン心療内科の活用がおすすめです。
自宅からスマホやパソコンで専門医と相談でき、診断書の相談やメンタルケアも受けられます。
まずは気軽にオンラインで相談してみませんか?
\今すぐ医師に相談できる/
適応障害で診断書がもらえない場合の対処法
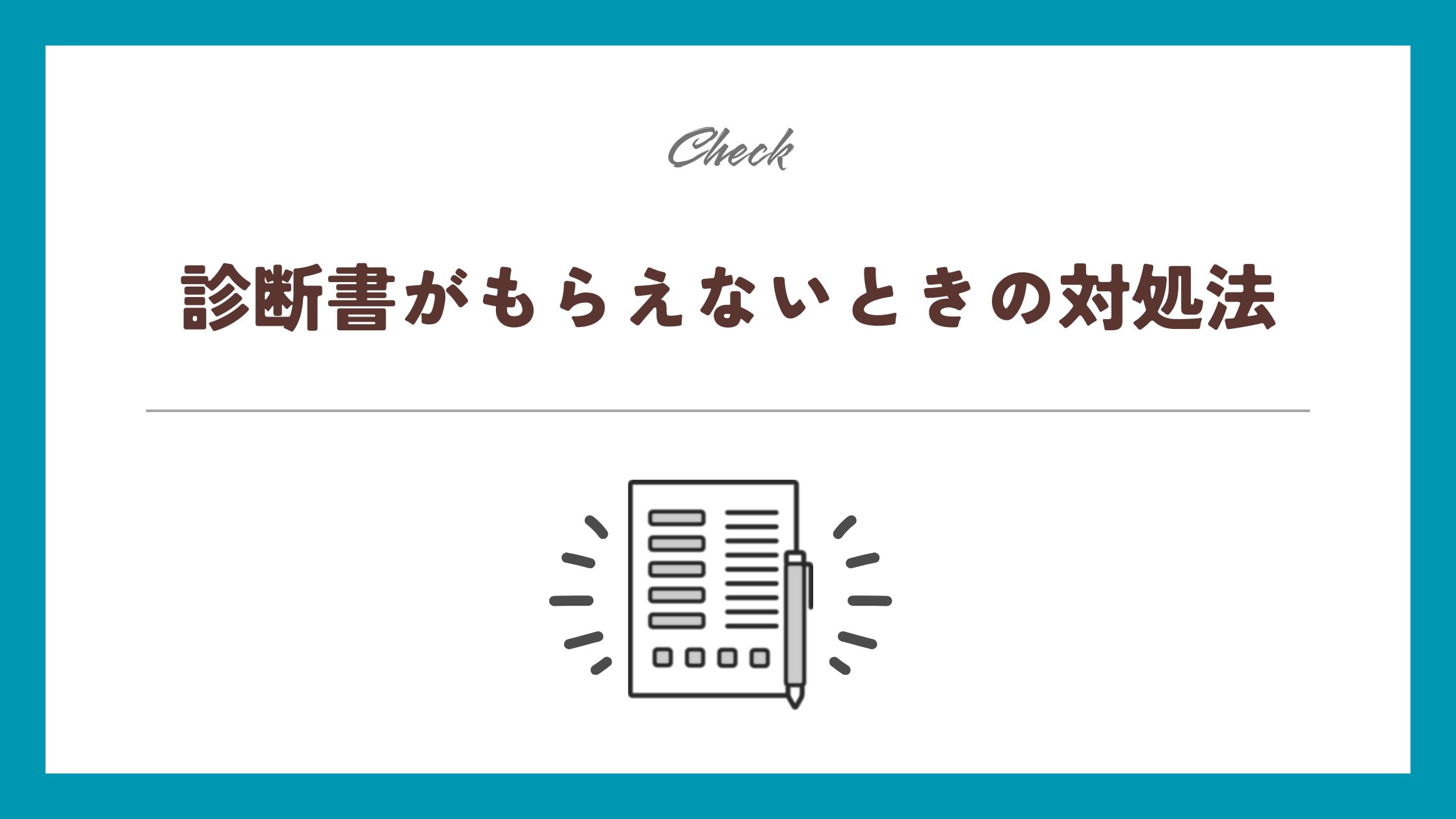
しっかり準備して診察に臨んだのに、医師から診断書がもらえなかったり発行が保留されたりすると、不安になりますよね。ですが、その場で諦めずに、いくつかの選択肢を知っておくことで状況を前に進められる可能性があります。ここでは、診断書が出ない理由への対処法と具体的な行動のポイントを解説します。
まずは担当医と改めてしっかりと話し合う
診断書がもらえなかったときは、まず担当医ともう一度じっくり話し合いましょう。
なぜ診断書が発行できないのか、その理由を率直に尋ねてみましょう。
例えば、下記のような医学的な理由があるはずです。
- まだ診断が確定していない
- 経過観察が必要
- 症状が診断書を出すほどではないと判断している
そのうえで、あなたの現状(症状、生活や仕事での困り事、診断書が必要な理由や緊急性)を、より具体的に伝えてください。
- 発行できない理由を理解しようとする姿勢を見せる
- 自分の症状が十分伝わるよう、より具体的に症状や困り事を説明する
- 診断書が必要な緊急性や、診断書がない場合の具体的な不利益を伝える
(例:このままでは仕事を続けられない、会社に理解してもらえない - 診断書発行のために、どのようにすれば良いかを尋ねる
(例:あと何回か受診して様子を見る、特定の症状について詳しく検査する - 診断書ではなく、「意見書」や「経過報告書」といった別の書類なら発行可能か相談する
誠実に自身の困っている状況を伝えることで、医師も改めて診断書発行の必要性を検討してくれる可能性があります。
セカンドオピニオンを検討する
担当医の判断に納得できない場合や別の意見を聞きたい場合は、他の医師に相談する「セカンドオピニオン」も一つの選択肢です。
現在診てもらっている担当医とは別の医師に意見を求め、診断や治療方針が妥当かどうかを確認するための制度。
主治医を変えることではなく、あくまで参考意見をもらうことで、より納得して治療や対応を決めるための選択肢です。
別の医師が改めて診察することで、担当医とは異なる診断に至ったり、現在の状態であれば診断書を発行できると判断したりする可能性もあります。
希望する場合は、現在の担当医に「紹介状」を依頼すると、これまでの経過が新しい医師に伝わりやすく、スムーズです。
担当医にセカンドオピニオン希望を伝えるのは気が引けるかもしれませんが、あなたの状態をより良くするための選択肢として、遠慮なく相談してみてください。
診断書以外の書類で対応できるか相談する
診断書は病名や休職期間など、比較的定型的な内容が記載されることが多いですが、医師によっては診断書ではなく、より柔軟な形式の書類で対応してくれる場合があります。
「診断書」という形式ではなくても、「意見書」や「経過報告書」といった形で、現在の心身の状態、それが仕事や日常生活に与える影響、会社側にお願いしたい配慮内容などを記載してもらうことが可能か、医師に相談してみましょう。
例えば、「適応障害とはまだ確定診断できないが、現在のストレス状況と心身の不調は、休養が必要な状態であることを示唆している」といった形で、診断名には踏み込まなくても、医師の医学的な見解を示すことで、会社側が状況を理解し、休職や配慮の必要性を検討してくれる場合があります。
特に、診断がまだ確定していない段階や、診断書を提出するほどではないと医師が判断している場合でも、このような代替の書類であれば発行可能となるケースがあります。
必要な手続きや提出先の規定によっては診断書が必須の場合もありますが、まずは会社や関係機関に相談し、診断書以外の書類でも受け付けてもらえるか確認してみることも一つの方法です。
精神科や心療内科など専門医療機関を受診する
これまで一般内科やかかりつけ医に相談していた場合は、専門の医療機関を受診してみるのもおすすめです。
適応障害は精神疾患の一種であり、精神科医や心療内科医は適応障害を含む精神疾患の診断・治療に関する専門的な知識と経験が豊富です。
あなたの症状が適応障害であるかどうかのより的確な診断や判断が期待できます。
「精神科」と聞くと抵抗があるかもしれませんが、心身の不調やストレスが原因の不調を専門的にみてもらうことが、早期の回復につながります。
| もらえない場合の対処法 | 具体的な行動・考慮事項 |
|---|---|
| 担当医と改めてよく話し合う | なぜ発行できないか理由を尋ねる。症状や困り事をより具体的に伝える。診断書がない場合の不利益を伝える。今後の治療方針を相談する。 |
| セカンドオピニオンを検討する | 別の精神科医/心療内科医を探す。担当医に紹介状の作成をお願いする。複数の専門家の意見を聞く。 |
| 精神科・心療内科など専門機関を受診する | 精神疾患の専門医の診察を受ける。診断や診断書発行に関する専門的な判断を仰ぐ。 |
| 診断書以外の書類を相談する | 意見書、経過報告書などで対応可能か医師に相談する。会社や提出先に代替書類が認められるか確認する。 |
診断書がもらえないと焦る気持ちは自然なことです。
すが、いくつもの選択肢がありますので、まずはできることから動いてみましょう。
「どこに相談したらいいかわからない」という方は、【オンライン心療内科】の利用も検討してみてください。
オンライン診療内科「メンクリ」なら通院の負担なく専門医と相談できるため、初めての方でも安心して相談できます。
\今すぐ医師に相談できる/
適応障害の診断書がないときの影響と代替手段
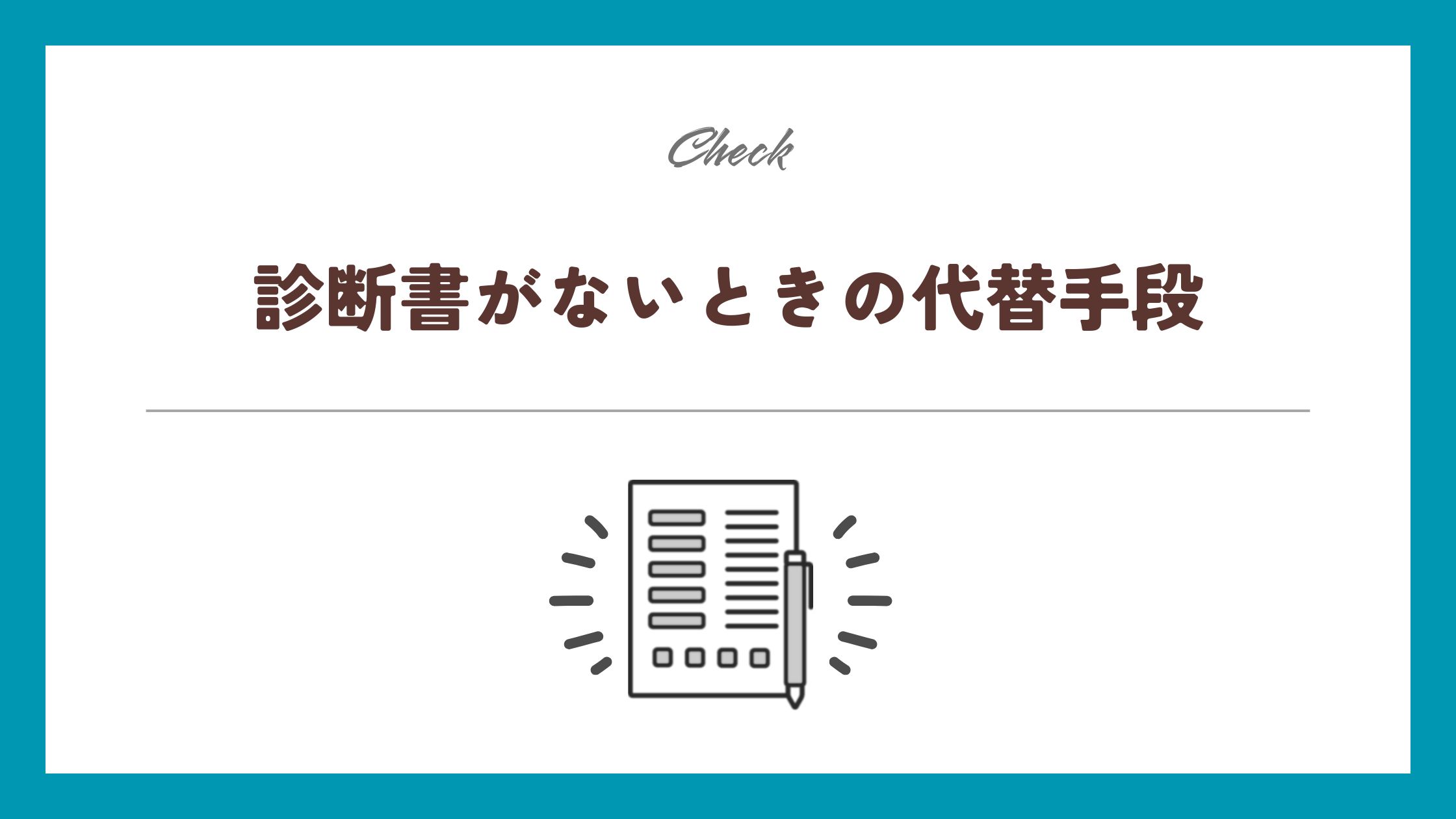
適応障害の診断書が出ない場合、休職や公的制度の申請で不利になったり、職場で必要な配慮が得られなかったりする可能性があります。ここでは、診断書がないときに考えられる影響と、それでも利用できる代替手段や支援策について紹介します。「診断書が出なくてどうしたらいいのか…」と悩む方は、ぜひ参考にしてください。
診断書がないと申請できない制度がある
傷病手当金や失業保険の特例申請には、医師の診断書が必須です。
傷病手当金
健康保険で休職中の生活費を補う「傷病手当金」は、医師が病名、発病日、労務不能と認めた期間などを記載する欄があり、この医師の証明がなければ申請自体が受理されません。
診断書がもらえないと、傷病手当金の申請ができない、あるいは申請が認められない可能性が高いです。
失業保険(特定理由離職者)
病気や不調が理由で離職した場合、通常より有利な条件で失業保険を受け取れるケースがあります。
自己都合退職の場合は通常7日間の待期期間に加え、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間がありますが、病気や怪我で働くことが困難になり離職した場合は、「特定理由離職者」として扱われ、この給付制限が適用されない場合があります。
特定理由離職者として認定されるためには、医師の診断書など、病気や体調不良が離職のやむを得ない理由であることを証明する書類の提出を求められることが一般的です。
診断書がない場合、この証明ができず、特定理由離職者として認められない可能性があります。
| 公的支援制度 | 診断書の必要性 | 診断書がない場合 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 必須 | 申請不可・不受理になる可能性がある |
| 失業保険 | 必要となる場合が多い | 自己都合退職扱いになる可能性がある |
職場での不利益や対応の難しさ
診断書がない状態で会社に休職や就業上の配慮を求める場合、会社が医学的な根拠に基づいた判断を下すことが難しくなります。
診断書がないと、会社の制度(休職制度など)を利用するための形式的な要件を満たせない可能性があり、結果として以下のような影響が出ることが考えられます。
- 休職が認められない
休職制度が利用できず、欠勤扱いになり給与カットや最悪の場合は退職を迫られる可能性がある
- 自己都合退職扱いになる
病気による退職と認められず、失業保険の条件が不利になる可能性がある - 必要な配慮が得られない
就業内容の軽減や異動などの配慮が得られないことがある
診断書がなくても、上司や人事に状況を伝えることは大切です。
口頭での説明だけでなく、具体的な症状や困っていることを書面にまとめて相談したり、意見書や経過報告書など簡易的な書類を医師に依頼して提出したりする方法も検討してみましょう。
会社によっては、診断書ほどの厳密な書類でなくても、社員の体調を把握し、適切な対応を検討してくれる場合があります。
会社の就業規則や相談窓口(産業医、社内カウンセラーなど)についても確認し、利用できる制度やサポートがないか探してみましょう。
診断書がなくても利用できる支援や相談先
適応障害による心身の不調があっても、診断書がないと利用できない公的支援制度が多いのは事実です。
しかし、診断書なしで利用できる、あるいは診断書以外の証明でも利用可能な代替手段や支援制度も存在します。
- 有給休暇
有給は原則診断書なしで取得できます。
- 会社の福利厚生制度
診断書の要否は会社の規定によりますが、比較的柔軟な対応が可能な場合もあります。 - 社内カウンセラー・産業医
診断書なしでも相談でき、会社へのアドバイスや配慮の提案をしてもらえる可能性があります。 - 自治体や地域の公的相談窓口
診断書なしで精神保健福祉センターや保健所などで無料相談が可能です。 - 民間カウンセリング・相談サービス
診断書の発行はできませんが、臨床心理士やカウンセラーによる心理的サポートが受けられます。
- 就労移行支援事業所など
診断名がついていなくても、利用可能な場合があります。 - 家族や友人からのサポート
一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人に相談し、支えを得ることも重要なセルフケアです。
診断書がもらえないと不安になりますが、それでも利用できる選択肢はあります。
「診断書がもらえるかどうか不安」「どう動けばいいかわからない」という方は、一度専門家に相談してみるのもおすすめです。
オンライン心療内科なら、自宅からスマホやPCで受診でき、必要な診断書や意見書についても相談可能です。
時間や場所の制約で受診を迷っている方は、ぜひオンラインの選択肢も検討してみてください。
\オンライン診療内科ならメンクリ!/
適応障害の診断書発行にかかる費用と期間
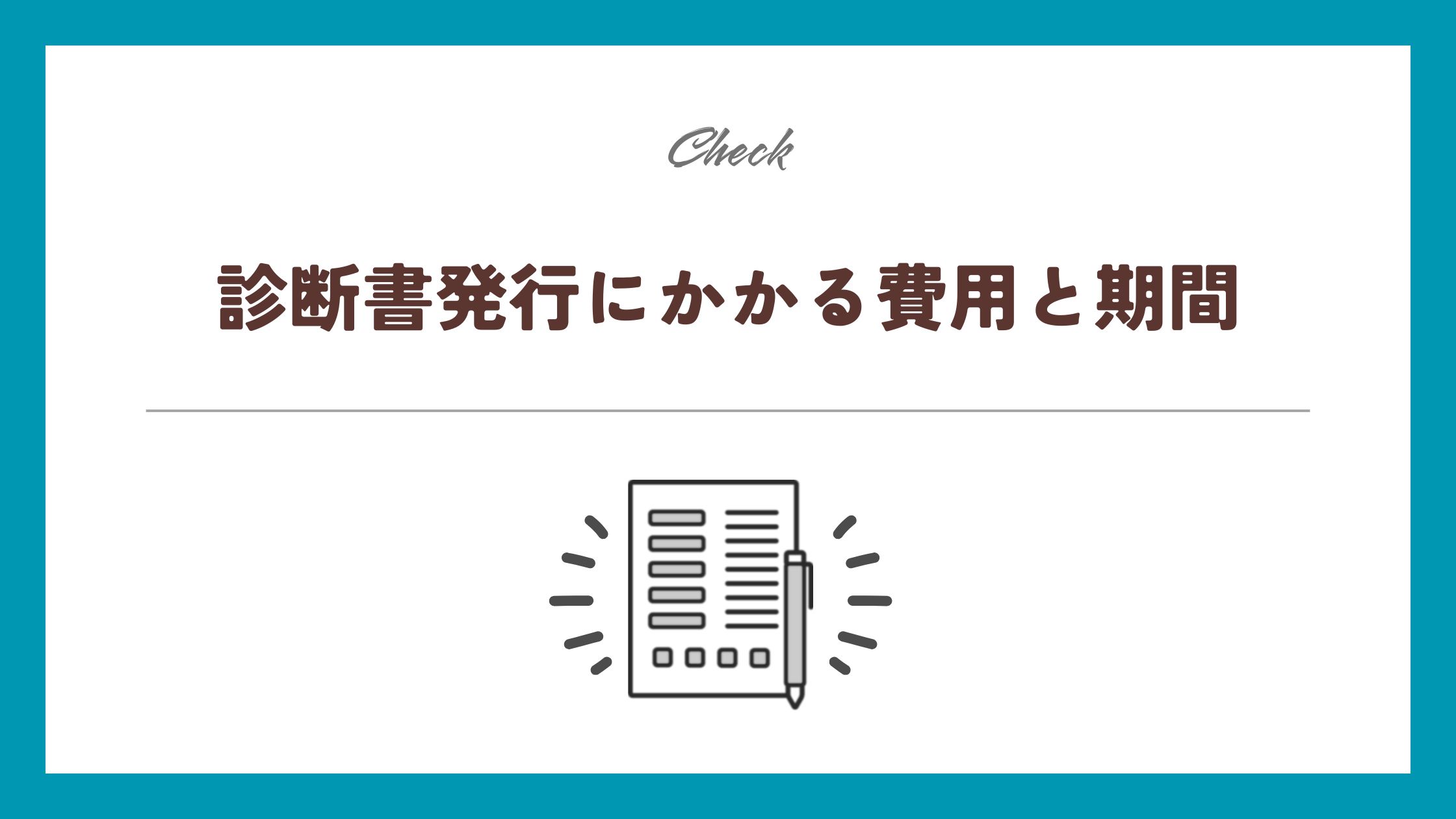
適応障害の診断書を発行してもらう際には、費用や発行までの日数に注意が必要です。特に「いつまでに提出が必要か」が決まっている場合は、早めに医師に相談しておくと安心です。
最近では、オンライン診療で相談から診断書の発行までスムーズに対応してくれる医療機関も増えているため、早めの行動がカギです。
\診断書即日発行も可能!/
診断書の発行費用相場
診断書の発行は健康保険が適用されず、各医療機関が自由に料金を設定しているため金額に幅があります。
一般的には、3,000円〜10,000円程度が相場とされています。
大学病院や総合病院などの大きな医療機関は、比較的高額になる傾向があり、個人クリニックのほうが比較的安いこともあります。
また、記載内容が複雑なもの(例:障害年金用の診断書)は、一般的な休職用の診断書よりも高額になることがあります。
診断書の発行を依頼する際に、受付などで事前に費用を確認しておくことをお勧めします。
多くの医療機関では、診断書作成に際して文書料(文書作成費用)として徴収されます。
即日発行は可能?かかる日数について
診断書の発行は、当日すぐにできるケースは少なく、数日〜1週間程度かかるのが一般的です。
医療機関によっては、急ぎの場合に対応してくれることもありますが、その場合でも即日ではなく、翌日や2~3日後に受け取り可能となることが多いです。
- 医師の診断確定までに複数回の診察が必要な場合がある
- 診断書作成には診察とは別の時間がかかる
- 書類内容の確認や押印など病院内の手続きを要する
- 土日祝や夜間は対応できない場合が多い
医師の診察時間外に書類作成や事務手続きが行われるため、時間がかかるのです。
急ぎの場合は、診断書が必要な期限とともに、その旨を医師や受付に伝え、対応が可能か相談してみましょう。
診断書が必要な期日が決まっている場合は、余裕をもって早めに医師に相談し、発行を依頼することが重要です。
オンライン診療がおすすめ
「休職したいが診断書が必要」「できるだけ早く相談したい」という方は、オンライン心療内科の活用もおすすめです。
スマホやパソコンから自宅で医師と相談でき、医療機関によっては診断書の郵送対応もしてくれます。
特に、通院のストレスや時間的な負担を減らしたい方、近くに専門の病院がない方にはオンライン診療が便利です。
適応障害の症状や今の困りごとについて、遠慮せず相談してみましょう。
\オンライン診療内科ならメンクリ!/
まとめ:適応障害の診断書取得に向けて
適応障害の診断書が出ないのは、医学的な判断や説明不足が原因の場合もあります。落ち込む必要はありません。大切なのは、自分の状態を正しく理解し、必要な支援を受けることです。
- 具体的な症状や困りごとをメモにまとめる
- 仕事や日常への影響、診断書が必要な理由を明確にする
- 診察では率直に伝える姿勢を大切に
- 担当医と改めて話し合い、理由を確認する
- セカンドオピニオンや専門医を検討する
- 意見書や経過報告書など代替書類の相談をする
- 有給休暇や社内窓口、公的相談機関を活用する
診断書をもらえず悩むのはつらいものです。オンライン診療なら、自宅から専門医に相談でき、必要に応じて診断書の発行も可能です。
オンライン診療がおすすめ
【免責事項】
本記事は、適応障害の診断書に関する一般的な情報提供を目的としています。
個々の症状、診断、治療方針、診断書発行の可否については、必ず医療機関を受診し、医師の判断を仰いでください。
記事中の情報に基づいた行為によって生じたいかなる結果についても、当サイトは責任を負いかねます。
また、公的支援制度や会社の制度については、変更される可能性があります。
最新の情報は各機関にお問い合わせください。