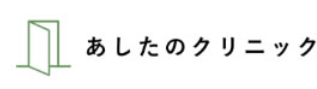身体の不調は誰にでも起こりうるものですが、検査を受けても原因が見つからないのに症状が続いたり、些細な不調に対して強い不安を感じて日常生活に支障が出たりすることがあります。
このような状態は、もしかすると「身体症状症」と呼ばれる疾患かもしれません。かつては「身体表現性障害」と呼ばれていましたが、診断基準が変更され、現在は身体症状症という診断名が使われることが増えています。
この記事では、身体症状症(旧称:身体表現性障害)について、どのような症状が現れるのか、なぜそのような状態になるのか、そしてどのように診断され、どのような治療法があるのかを詳しく解説します。体の不調で悩んでいるけれど、原因が分からず不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。この疾患への理解を深め、回復への一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
身体表現性障害の概要とDSM-5での変更点
身体表現性障害(身体症状症)とは?精神疾患としての位置づけ
身体表現性障害、現在の精神医学の診断基準(DSM-5)では主に「身体症状症」として位置づけられている疾患は、一つ以上の身体症状が存在し、その症状に対して過剰な思考、感情、または行動が伴うことによって特徴づけられます。ここでいう身体症状は、医学的に説明できるものであっても、あるいは説明できないものであっても診断の対象となり得ます。重要なのは、症状そのものの重さや医学的な説明の可否ではなく、症状に対する個人の捉え方や反応の仕方が、著しい苦痛や日常生活上の障害を引き起こしている点です。
この疾患は、単に「体の弱い人」や「気の持ちよう」といった問題として片付けられるべきものではありません。脳機能の偏り、心理的な要因、過去の経験、社会的要因などが複雑に絡み合って発症すると考えられており、精神疾患の一つとして、専門的な理解と治療が必要とされています。症状による苦痛は現実のものであり、患者さんのQOL(生活の質)を著しく低下させることがあります。仕事や学校に行けなくなったり、人との交流を避けたりするなど、社会生活に大きな影響を及ぼすこともあるのです。
「身体症状症」という診断名は、身体の不調という表面的な現象だけでなく、その背後にある認知(考え方)、情動(感情)、行動の偏りに焦点を当てたものであり、この疾患の本質をより正確に捉えようとする現代精神医学のアプローチを示しています。
DSM-5における身体症状症への変更点
精神疾患の診断基準として世界的に広く用いられている「精神疾患診断統計マニュアル(DSM)」は、改訂を重ねてきました。かつてDSM-IVでは、「身体表現性障害群」として、身体化障害、疼痛性障害、心気症、転換性障害など、複数の診断名が存在していました。これらの診断は、身体症状の性質や医学的説明の有無などに重点が置かれていましたが、診断基準が重複しやすく、臨床現場で使いにくいという課題も指摘されていました。例えば、身体化障害と診断される多くの患者さんが、同時に心気症や疼痛性障害の基準も満たすといった状況が見られました。
DSM-5への改訂(2013年)では、これらの課題を踏まえ、「身体症状症および関連症群」という新たなカテゴリーが設けられました。このカテゴリーには、身体症状症、病気不安症(旧心気症の一部)、転換症(機能性神経症状症)、人為症などが含まれます。中でも最も大きな変更点は、「身体症状症」の概念が導入されたことです。
DSM-5の身体症状症の診断基準は、以下のような要点を含んでいます。
- 基準A: 1つ以上の身体症状が存在し、苦痛を引き起こすか、日常生活に重大な支障をきたしている。
- 基準B: 身体症状や関連する健康への懸念に対して、以下のいずれか1つ以上が存在する。
- 症状の重篤さに関する不釣り合いで持続的な思考。(例:「この頭痛はきっと脳腫瘍のサインに違いない」と過度に心配する)
- 健康や症状に関する過剰で持続的な不安。(例:検査で異常なしと言われても「見落とされているのではないか」と不安が消えない)
- これらの症状や健康への懸念に不釣り合いなほど多くの時間とエネルギーを費やすこと。(例:一日中インターネットで病気について検索したり、頻繁に医療機関を受診したりする)
- 基準C: 身体症状は必ずしも持続的でなくてもよいが、身体症状症である状態は持続的である(通常6ヶ月以上)。
この新しい診断基準の最も重要な点は、身体症状そのものが医学的に説明できるか否かを必須要件としないことです。たとえ高血圧や糖尿病などの医学的な病気による症状(例:頭痛や倦怠感)であっても、それに対して基準Bのような過剰な思考、感情、行動が伴い、苦痛や機能障害が生じている場合は、身体症状症と診断されうるのです。これにより、「原因不明の身体症状」だけでなく、「既存の身体疾患に伴う、症状への過剰な反応」も捉えることができるようになりました。
このDSM-5での変更は、身体の不調を訴える患者さんを、単に「身体的な病気があるかないか」という二元論で捉えるのではなく、症状に対する心理的・行動的な反応も含めたより包括的な視点で理解しようとする流れを反映しています。旧来の身体化障害や心気症と診断されていた方の多くは、DSM-5では身体症状症と診断される可能性が高いと考えられます。この診断概念の変遷は、この疾患の病態理解が進み、「気のせい」といった精神論ではなく、脳と心、身体の相互作用による複雑なメカニズムによって生じる状態として捉えられるようになったことを示しています。
身体表現性障害の主な症状と特徴
様々な身体症状の現れ方
身体症状症で現れる身体症状は、特定の臓器や部位に限定されず、非常に多岐にわたります。人によって、また時期によって、現れる症状やその性質が変化することも少なくありません。代表的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 疼痛(痛み):
- 最も頻繁に見られる症状の一つです。
- 部位は頭痛、首や肩の痛み、腰痛、胸痛、腹痛、関節痛、手足の痛みなど、体のあらゆる場所に起こり得ます。
- 痛みの性質も様々で、ズキズキする、締め付けられる、チクチクする、重い、焼けるような感じなどと表現されます。
- 特定の動きや状況と関連しているように感じられることもあれば、原因が全く思い当たらないこともあります。
- 消化器症状:
- 吐き気、腹部膨満感、胃痛、下痢、便秘、呑酸(胸焼けのような不快感)などがよく見られます。
- 過敏性腸症候群(IBS)の診断基準を満たす場合もありますが、IBSの症状に加えて過剰な健康不安や苦痛が伴う場合に身体症状症が考慮されることがあります。
- 神経症状:
- めまい、立ちくらみ、しびれ感、感覚の異常(ピリピリ、ジンジンするなど)、脱力感、体の震え、発汗などが含まれます。
- これらの症状が特定の神経疾患を疑わせる場合もありますが、検査で異常が見つからないことが一般的です。
- かつて転換性障害と呼ばれた症状(麻痺、失声、視野狭窄など)も、医学的に説明できない身体症状として、身体症状症や転換症として診断され得ます。
- 心血管・呼吸器症状:
- 動悸(心臓がドキドキする)、息切れ、胸部圧迫感や不快感などが挙げられます。
- これらの症状はパニック障害でも見られますが、パニック発作のような急激なものではなく、比較的持続的に感じられる場合もあります。心疾患との鑑別が重要です。
- その他の症状:
- 全身の強い疲労感や倦怠感。
- 睡眠障害(寝つきが悪い、途中で目が覚める、熟睡できない)。
- 皮膚のかゆみや感覚異常。
- 喉の違和感、つかえ感。
- 性機能に関する不調。
- 月経に関する不調(女性の場合)。
これらの症状は、一つだけ現れることもありますが、多くの場合、複数の症状が同時に、あるいは時期をずらして現れます。症状の現れ方や強さは、その時の体調やストレス、心理状態によって変動することがあります。また、症状が体のあちこちを移動するように感じられることも、この疾患の特徴の一つです。
医学的な検査で異常が見つからない場合でも、患者さんにとってはこれらの症状は現実のものであり、大きな苦痛を伴います。この「苦痛」は、単なる身体的な不快感だけでなく、症状がもたらす不安や恐怖、絶望感といった精神的な苦痛も含んでいます。
症状への過剰なとらわれと苦痛
身体症状症の核となる特徴は、**身体症状そのものに加えて、あるいはそれ以上に、その症状に対する過剰な思考、感情、行動が苦痛や障害の原因となっている**点です。これは、他の身体疾患や健康な人でも起こりうる一時的な体の不調とは異なる、この疾患特有の様相です。
具体的には、以下のような「過剰なとらわれ」が見られます。
- 過剰な思考(認知的側面):
- 症状の重篤さに関する不釣り合いで持続的な思考: 些細な身体感覚を重篤な病気の兆候ではないかと過度に心配します。「この痛みはきっと進行したがんだ」「このめまいは脳梗塞の前触れかもしれない」といった考えに囚われて離れられなくなります。
- 身体や健康への継続的な監視: 自分の体の感覚に過敏になり、常に体の異変がないか注意深くチェックします。少しでもいつもと違う感覚があると、強い不安を感じます。
- 健康情報への過剰な関心: インターネットなどで病気に関する情報を調べ続け、自分の症状と合致する可能性のある病気を見つけては、さらに不安を募らせます。
- 過剰な感情(情動的側面):
- 健康や症状に関する過剰で持続的な不安: 検査で異常がないと言われても、医師の診断や検査結果を信用できず、「見落としがあるのではないか」「まだ発見できない珍しい病気かもしれない」といった強い不安が持続します。この不安は、症状が出ている時だけでなく、症状がない時でも健康全般に対して向けられることがあります。
- 症状に伴う抑うつや絶望感: 症状が続くこと、あるいは原因が分からないことに対して、気分がひどく落ち込んだり、絶望感を感じたりします。「もう良くならないのではないか」「このままどうなってしまうのだろう」といった悲観的な感情に囚われます。
- 過剰な行動(行動的側面):
- 不必要な医療機関の頻繁な受診: 症状への不安から、様々な診療科を渡り歩き、何度も検査や診断を求めます。医師から異常がないと言われても安心できず、別の医療機関を受診することを繰り返します(ドクターショッピング)。
- 異常な健康チェック: 体温や血圧、脈拍などを頻繁に測ったり、体にできものがないか鏡で繰り返し確認したりするなど、過剰な自己チェックを行います。
- 症状を避けるための不適応な行動: 症状が出ることを恐れて、特定の活動(運動、外出、仕事など)を避けたり、特定の食べ物を極端に制限したりするなど、日常生活に大きな制限をかけてしまいます。
- 過剰な病気関連の相談: 家族や友人に自分の症状について繰り返し話したり、安心を求めたりします。
これらの過剰な思考、感情、行動は、実際の身体症状の程度や医学的な所見に見合わないほど強いことが特徴です。そして、これらの「とらわれ」こそが、身体症状そのものによる不快感以上に、**患者さんの精神的な苦痛を増大させ、日常生活や社会生活に著しい支障をきたす主な原因**となります。
例えば、軽い頭痛があったとします。健康な人であれば鎮痛剤を飲むか、休息を取れば治るだろうと考え、あまり深く気にしないかもしれません。しかし、身体症状症の人は、その頭痛を「脳腫瘍のサインだ」と強く確信し、激しい不安に襲われ、救急病院を受診したり、インターネットで脳腫瘍の情報を何時間も調べ続けたりするかもしれません。この場合、苦痛の主体は「頭痛」そのものというよりは、「脳腫瘍かもしれない」という思考と、それに伴う激しい「不安」なのです。
このように、身体症状症では、身体の不調に対する誤った解釈や過剰な反応が、病気の悪循環を生み出し、患者さんを苦しめることになります。
身体表現性障害の原因・背景
身体症状症の発症は、単一の明確な原因で説明できるものではありません。多くの場合は、**複数の要因が複雑に絡み合い、相互に影響し合うことで発症すると考えられています。**これらの要因は、大きく分けて心理的要因、社会的要因、そして生物学的要因に分類できます。
考えられる心理的・社会的要因
- ストレス:
- 慢性的または急性のストレスは、身体症状症の発症や悪化の重要な要因となり得ます。仕事の過労、人間関係の悩み、家族の問題、経済的な困難など、様々なストレスが身体の不調として現れやすくなることがあります。
- ストレスに対する個人の対処能力や、ストレスをどのように捉えるかといった認知的な側面も影響します。
- 過去のトラウマ体験:
- 特に幼少期の身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(育児放棄)などのトラウマ体験は、大人になってからの身体症状症の発症リスクを高めることが知られています。
- 過去のトラウマ体験が、自身の身体や安全に対する不安感を高めたり、感情を適切に処理することを困難にしたりすることが考えられます。
- 感情の表現が苦手(身体化):
- 自分の感情、特にネガティブな感情(怒り、悲しみ、不安など)を言葉で適切に表現することが苦手な人がいます。このような場合、感情が身体的な不調として現れることがあります。これを「身体化」と呼びます。
- 感情を抑圧したり、無視したりする傾向が強いと、身体が代わりにSOSを発しているのかもしれません。
- 性格傾向:
- 完璧主義、生真面目すぎる、物事をコントロールしたがる、融通が利かないといった性格傾向を持つ人は、ストレスを溜め込みやすく、身体症状症を発症しやすい傾向があると言われています。
- また、不安を感じやすい気質や、破局的思考(最悪の事態を想定して過剰に心配する考え方)に陥りやすい傾向も関連しています。
- 過去の病気や医療体験:
- 過去に重い病気にかかった経験がある、あるいは家族が病気で苦しんだ経験がある場合、自分自身の身体の些細な不調に対しても過剰に心配しやすくなることがあります。
- 過去の医療体験が不信感やトラウマにつながり、医療への過剰な依存や回避を引き起こすこともあります。
- 養育環境:
- 幼少期に、親が子供の身体の不調に対して過剰に心配したり、病気を理由に過保護になったりする環境で育った場合、大人になってからも身体の不調に過敏に反応しやすくなることがあります。
- また、感情の表現を抑制されるような養育環境も、身体化を促す可能性があります。
- 家族からの注目:
- 病気になった時に家族から特別な注目や心配を得られた経験があると、無意識のうちに身体症状がコミュニケーションや愛情を得る手段となってしまうことがあります。これは決して意図的に病気を装うということではなく、無意識的なパターンです。
- 社会的孤立やサポート不足:
- 信頼できる友人や家族が少なく、悩みを打ち明けられる相手がいない場合、ストレスや不安を一人で抱え込み、身体症状として現れやすくなることがあります。
これらの心理的・社会的要因は、単独で作用するだけでなく、相互に影響し合って、身体症状への過剰な反応が生じやすい土壌を作り出すと考えられます。
身体化障害との関連性
「身体化障害」は、DSM-IVにおいて身体表現性障害群に含まれていた診断名の一つです。その診断基準は、**複数の、医学的に十分に説明できない身体症状が長期間(通常は数年間)にわたって続き、それによって著しい苦痛や機能障害が生じていること**を主な要件としていました。症状は体の様々な系(疼痛、消化器、神経、性器など)にわたって現れることが特徴でした。
前述のように、DSM-5ではこの身体化障害の概念が見直され、より広い概念である**「身体症状症」に統合**されました。これは、身体化障害の診断基準が「医学的に説明できない」という点に強く依存していたため、医学知識の進歩によって症状が説明可能になった場合に診断が変わってしまうという不安定さがあったこと、また、症状の医学的説明の有無にかかわらず、症状に対する過剰なとらわれが患者さんの苦痛や機能障害の主な原因となっている症例が多く見られたことによります。
したがって、旧来の身体化障害と診断されていた多くの症例は、DSM-5では身体症状症と診断されることになります。身体症状症は、身体化障害が重視していた「複数の、医学的に説明できない身体症状」という点に加え、「症状に対する過剰な思考、感情、行動」という側面に焦点を当て、**症状の医学的説明の可否を診断の必須要件から外した**点が最大の違いです。
この関連性を理解することは、身体症状症が単に「身体的な病気がないのに体の不調を訴えている」という状態ではなく、**身体の感覚や信号を脳や心がどのように処理し、それに対してどのような心理的・行動的な反応を示すか**という、心身の複雑な相互作用によって生じる疾患であるという認識を深める上で重要です。身体化障害の研究を通して蓄積された知見は、現在の身体症状症の病態理解や治療法の開発に活かされています。単に「気のせい」と捉えるのではなく、脳機能の偏りや心理的なプロセス、過去の経験などが関与する複雑な病態として、より深く理解されるようになったのです。
身体表現性障害の診断方法
身体症状症の診断は、他の身体的な病気との鑑別を徹底的に行うこと、そして精神科医による詳細な評価に基づいて行われます。
身体的な病気との鑑別診断
身体症状症の患者さんは、様々な身体症状を訴えて医療機関を受診します。そのため、診断の最初のステップであり、最も重要なステップは、**訴えている身体症状の原因となる他の医学的な病気がないかを徹底的に調べる**ことです。
患者さんは、まずは内科や整形外科、神経内科、消化器内科など、症状に関連すると思われる診療科を受診することが一般的です。担当医は、患者さんの症状について詳しく問診を行い、身体診察を行います。必要に応じて、血液検査、尿検査、レントゲン、CTスキャン、MRI、内視鏡検査など、様々な検査が行われます。
この段階での医師の役割は非常に重要です。患者さんの訴える苦痛を真摯に受け止め、安易に「気のせい」と決めつけず、**考えられる身体的な病気を丁寧に除外していく**必要があります。一方で、過剰な不安に基づいた不必要な検査を繰り返すことは、医療費の増大や患者さんの医療機関への過度な依存を招く可能性があるため、バランスの取れたアプローチが求められます。
検査の結果、訴えている身体症状を十分に説明できる医学的な病気が見つからなかった場合、あるいは、身体的な病気は存在するものの、症状に対する患者さんの思考、感情、行動が病気や医学的所見に見合わないほど過剰であると判断された場合に、身体症状症や他の精神疾患の可能性が考慮され、精神科や心療内科への受診が勧められることがあります。
重要なのは、たとえ身体的な病気が見つからなかったとしても、患者さんの苦痛は「気のせい」ではなく、現実のものであるということです。身体的な病気がないと診断されたとしても、それは「病気ではない=苦痛はない」ということではなく、「身体的な検査では異常が見つからない別の原因がある」ということを意味します。その「別の原因」の一つとして、身体症状症が考えられるのです。
精神科医による評価と診断基準
身体的な病気との鑑別を経て、精神科や心療内科を受診した場合、精神科医による詳細な評価が行われます。この評価に基づいて、DSM-5の診断基準などが用いられ、診断が確定されます。
精神科医が行う評価は、以下のような点を含みます。
- 詳細な病歴聴取(問診):
- 現在の症状: どのような身体症状があるか、いつから始まったか、症状の性質、強さ、持続時間、変動パターン、悪化させる要因、軽減させる要因などを具体的に、時系列に沿って詳しく尋ねます。
- 症状に対する考え方、感情、行動: 症状についてどのように考えているか、どのような感情(不安、恐怖、悲しみ、怒りなど)を感じているか、症状に対してどのような行動(医療機関への受診、インターネット検索、活動制限など)をとっているかについて詳しく尋ねます。これが身体症状症の診断において最も重要な部分です。
- 日常生活への影響: 症状によって仕事、学業、家事、趣味、人間関係などにどのような影響が出ているかを確認します。
- 精神疾患の既往: 過去にうつ病、不安障害、パニック障害などの精神疾患にかかったことがあるか、治療を受けたことがあるかを確認します。
- ストレス状況: 現在、どのようなストレス(仕事、家庭、対人関係など)を抱えているかについて尋ねます。
- 生育歴、家族歴: 幼少期の経験、家族の病歴(身体的なもの、精神的なもの)、家族構成や関係性などについて尋ねることがあります。これは、疾患の背景にある心理的・社会的要因を探る上で重要です。
- アルコールや薬物の使用状況: 身体症状や精神症状に影響を与える可能性のあるアルコールや市販薬、サプリメントなどの使用状況を確認します。
- 精神医学的診察:
- 問診の中で、患者さんの話し方、表情、態度、思考の内容、感情の表出、現実検討能力(物事を客観的に捉える能力)、幻覚や妄想の有無などを観察し、精神状態を評価します。
- 心理検査:
- 必要に応じて、症状の程度(不安、抑うつなど)や性格傾向、ストレスへの対処スタイルなどを評価するために、質問紙法や投影法などの心理検査が行われることがあります。
これらの評価に基づき、精神科医はDSM-5の身体症状症診断基準に照らし合わせて診断を行います。
DSM-5 身体症状症 診断基準の適用例
例えば、ある患者さんが「原因不明の胸痛」を訴えていたとします。内科で心臓や肺、消化器などに異常がないことが確認されました。精神科を受診した際、その患者さんは胸痛に対して以下のような様子が見られました。
- 思考: 「これはきっと珍しい心臓病に違いない」「突然心臓が止まってしまうのではないか」と常に考え、他のことを考えられない。
- 感情: 強い不安と恐怖を感じており、夜も眠れないことがある。
- 行動: インターネットで心臓病について一日中調べ、毎日のように脈を測る。胸痛が出ると救急車を呼ぼうとする。
この場合、身体症状(胸痛)があり(基準A)、それに対して過剰な思考、感情、行動が見られ(基準B)、これらの状態が6ヶ月以上続いている(基準C)と判断されれば、身体症状症と診断される可能性が高くなります。たとえ後に胸痛の原因となる軽い逆流性食道炎が見つかったとしても、胸痛に対する過剰な反応(重篤な病気への確信、激しい不安、頻回な受診など)が続いている場合は、身体症状症が併存していると判断されることもあります。
診断の目的は、患者さんの状態を正しく理解し、適切な治療につなげることです。診断がつくことで、患者さん自身も自分の抱える苦痛が「気のせい」ではなく、医療的なサポートが必要な状態であることを認識でき、治療への主体的な取り組みにつながる第一歩となります。診断はあくまで通過点であり、その後の治療こそが回復への鍵となります。
身体表現性障害の治療法
身体症状症の治療は、単一の治療法だけで完結するものではなく、患者さんの状態に合わせて複数のアプローチを組み合わせて行うことが一般的です(集学的治療)。治療の目標は、**症状の完全な消失を目指すというよりは、症状による苦痛を軽減し、症状に対する過剰なとらわれを減らし、日常生活や社会生活における機能障害を改善し、QOLを高めること**に重点が置かれます。
治療を進める上で最も重要なのは、**患者さんと治療者(医師、心理士など)との間に信頼関係を築き、協力して治療に取り組むこと**です。患者さんが自身の症状や診断について理解し、治療の目標を共有することが、治療効果を高める上で不可欠となります。
精神療法(カウンセリングなど)
身体症状症の治療において、精神療法は中心的な役割を担います。特に、症状に対する過剰な思考、感情、行動の偏りを修正することに焦点を当てた精神療法が有効であることが示されています。
- 認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy):
- 身体症状症に対して最も多くの科学的根拠があるとされている治療法です。
- 患者さんが抱える症状に関する「認知」(思考や信念)と、それに基づく「行動」に働きかけ、問題となっているパターンを修正していくことを目指します。
- 具体的には、
- 症状に関する誤った認知の特定と修正: 「この症状はきっと恐ろしい病気のサインだ」「少しでも体の不調があれば危険だ」といった、症状に対する非現実的または破局的な思考パターンを特定し、より現実的でバランスの取れた考え方に修正していく練習を行います。
- 過剰な健康チェックや安心を求める行動の軽減: 頻繁な自己チェックや医療機関への受診、インターネットでの医療検索、家族への過剰な相談といった、不安を一時的に軽減するために行っているが、結果的に不安を維持・増大させている行動を減らしていくための計画を立て、実践します。
- 身体感覚への過敏性の軽減: 身体の些細な感覚に過剰に注意を向ける癖を修正し、身体感覚をより客観的に受け止められるようにする練習を行います。
- 曝露療法(Exposure Therapy): 症状が出ることや、症状に関連する活動(かつてはできていたのに症状への不安から避けている活動など)に対する不安を和らげるために、不安を招く状況や活動に段階的に取り組んでいくことがあります。例えば、めまいが怖くて外出できない人であれば、安全な場所から少しずつ外出する練習をしていきます。
- リラクゼーション技法の習得: 腹式呼吸や筋弛緩法など、不安や身体的な緊張を和らげるためのリラクゼーション技法を学び、実践します。
- CBTは、構造化されたセッションで行われ、通常は週に1回程度、数ヶ月から1年程度の期間で行われることが多いです。ホームワーク(宿題)として、セッションで学んだ内容を日常生活で実践することも含まれます。
- 力動的精神療法:
- 身体症状の背景にある無意識的な葛藤、過去の満たされなかった欲求、感情を抑圧する癖、トラウマ体験などが、身体症状として現れている可能性があるという視点から、これらの深層にある心理的な問題を探求し、理解を深めることを目指します。
- 症状が象徴するものや、症状が患者さんの生活の中で果たしている役割(例:苦しい状況から一時的に逃れる手段となっている、周囲から注目を得る手段となっているなど)について、患者さんと治療者が一緒に考えていきます。
- 支持的精神療法:
- 患者さんの苦痛や困難に寄り添い、共感的な態度で話を聞き、安心感を提供することに重点を置いた精神療法です。
- 病気について正しく理解することを助け、症状との付き合い方や、日常生活で困っていることへの対処法を一緒に考えます。特に、治療の初期段階で患者さんとの信頼関係を築く上で重要となります。
- 集団療法:
- 同じように身体症状症で悩む人々が集まり、互いの経験や悩み、対処法などを共有する中で、孤立感を軽減し、自分だけではないという安心感を得たり、他の人の体験から学びを得たりすることができます。
これらの精神療法は、医師だけでなく、臨床心理士や公認心理師などの専門家によって行われます。どの精神療法が適しているかは、患者さんの状態や性格、治療者との相性によって異なります。
薬物療法による症状の緩和
身体症状症に対する特効薬は現在のところありません。しかし、薬物療法は、**併存する精神疾患(うつ病や不安障害など)の症状を緩和したり、身体症状そのもの(痛みや不眠など)の苦痛を軽減したりする目的**で用いられることがあります。薬物療法は精神療法を補完する役割を担うことが多く、薬だけで身体症状症の根本的な解決は難しいことを理解しておく必要があります。
使用される主な薬剤は以下の通りです。
- 抗うつ薬:
- 特に選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)が使用されることが多いです。
- これらの薬剤は、脳内の神経伝達物質のバランスを調整し、うつ症状や不安症状だけでなく、一部の身体症状(特に慢性疼痛や消化器症状)にも効果を示すことがあります。
- 身体症状症に対して抗うつ薬を使用する場合、うつ病の治療に比べて比較的少量から開始し、効果や副作用を見ながら慎重に用量を調整していくことが一般的です。
- 効果が現れるまでに数週間かかることがあります。
- 抗不安薬:
- 強い不安やパニック症状が一時的に見られる場合に、症状を抑えるために短期間使用されることがあります。
- しかし、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は依存性のリスクがあるため、漫然と長期間使用することは避け、必要最小限の使用にとどめることが重要です。
- その他の薬:
- 痛みが強い場合には、神経障害性疼痛に効果のある薬剤や、必要に応じて鎮痛薬が処方されることがあります。
- 不眠が強い場合には、睡眠薬が処方されることがありますが、これも依存性や副作用に注意が必要です。
- 消化器症状が強い場合には、整腸剤や胃薬などが併用されることもあります。
薬物療法は、医師の指示に従って正しく服用することが非常に重要です。自己判断で服用量を変更したり、服用を中止したりすることは危険です。薬の効果、副作用、服薬期間などについて、医師と十分に相談し、疑問点があれば質問するようにしましょう。
日常生活でのセルフケアと工夫
身体症状症の治療効果を高め、症状とうまく付き合いながら回復していくためには、日常生活でのセルフケアが非常に重要です。患者さん自身が主体的に取り組むことで、症状による苦痛を軽減し、より健康的な生活を送ることができるようになります。
以下に、セルフケアとして有効な工夫をいくつかご紹介します。
- ストレス管理:
- ストレス源の特定と対処: どのような状況や出来事がストレスになっているのかを特定し、可能な範囲でそのストレス源を減らす、あるいはストレスに対する考え方や捉え方を変える工夫をします。
- リラクゼーション技法の活用: 腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、瞑想(マインドフルネス)、ヨガ、ストレッチなど、自分に合ったリラクゼーション法を見つけ、毎日実践する習慣をつけましょう。これにより、心身の緊張を和らげ、不安を軽減することができます。
- 十分な休息と睡眠: 規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠時間を確保することは、心身の回復にとって不可欠です。
- 適度な運動:
- ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳など、無理のない範囲で定期的に体を動かすことは、ストレス解消や気分転換になるだけでなく、身体感覚への肯定的な気づきを促し、不安を軽減する効果も期待できます。
- 運動は、症状への不安から活動を制限している患者さんにとって、身体への信頼を取り戻すための一歩となることもあります。最初は短時間・低強度から始め、徐々に慣らしていきましょう。
- 健康的な生活習慣:
- バランスの取れた食事を心がけ、加工食品やカフェイン、アルコールの過剰摂取は控えることが望ましいです。
- 喫煙している場合は、禁煙を検討しましょう。
- 感情表現の練習:
- 自分の感情を言葉にする練習をしましょう。信頼できる家族や友人、カウンセラーに話を聞いてもらう、日記に気持ちを書き出すなどが有効です。感情を溜め込まずに適切に表現することは、身体化を防ぐ上で役立ちます。
- 活動量の調整:
- 症状への不安から過度に活動を制限している場合は、少しずつ活動範囲を広げていく練習をします。セラピストと相談しながら、不安階層表を作成し、段階的に取り組むことが効果的です。
- 一方で、無理をしすぎて症状を悪化させないよう、体調に合わせて休息もきちんと取るようにしましょう。
- 症状との向き合い方(マインドフルネスなど):
- 症状を完全に消そうとするのではなく、「症状があるものとして、それとどう付き合っていくか」という視点を持つことが重要です。マインドフルネスの考え方を取り入れると、症状に評価を加えずに注意を向け、ありのままを受け流す練習ができます。これにより、症状に対する過剰な反応を減らすことが期待できます。
- 趣味や楽しみを持つ:
- 自分が楽しめる活動や趣味に時間を使うことは、症状から注意をそらし、気分転換になり、生活の質を高める上で非常に重要です。
- 支援システムを活用する:
- 家族や友人など、信頼できる人に支えを求めることは、孤立感を軽減し、心の安定につながります。
- 同じ悩みを持つ人が集まる自助グループに参加することも、共感を得られたり、具体的な対処法を学べたりする点で有効です。
セルフケアは、治療の補助ではなく、回復に向けて患者さん自身が主体的に取り組むための重要な要素です。これらの工夫を日常生活に取り入れ、症状との付き合い方を学ぶことで、徐々に苦痛を軽減し、より自分らしい生活を取り戻すことが可能になります。
どこに相談・受診すれば良いか
身体の不調があり、内科などの医療機関で様々な検査を受けても原因が見つからない、あるいは身体的な病気はあるものの、症状に対する不安や苦痛が強く、日常生活に支障が出ているといった場合は、身体症状症をはじめとする心身の関連する疾患の可能性が考えられます。このような場合に相談・受診を検討すべきなのは、**精神科や心療内科**です。
専門の医療機関(精神科・心療内科)の選び方
- 精神科と心療内科の違い:
- 精神科: 主に統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、依存症など、心の病気全般を専門に扱います。精神療法や薬物療法を用いて、心の健康回復を目指します。
- 心療内科: 主に心身症(心理的なストレスが身体症状として現れる病気、例:胃潰瘍、過敏性腸症候群、高血圧、気管支喘息など)や、身体疾患に伴う精神的な問題、そして身体症状症などを専門に扱います。身体的な側面と精神的な側面の両方からアプローチし、心と体の両方のバランスを整えることを目指します。
- 身体症状症は、心身の相互作用が強く関わる疾患であるため、**心療内科がより専門的に扱っている傾向があります。**しかし、精神科でも身体症状症の診療経験が豊富な医師は多くいます。どちらの科を受診しても構いませんが、特に身体症状が中心で、その背後にある心の問題も同時に見てほしいという場合は、心療内科の方がスムーズな場合もあります。
- 病院(クリニック)の選び方:
- 情報収集:
- インターネットで「地域名 精神科 身体症状症」「地域名 心療内科 身体症状症」「地域名 身体症状症 専門」といったキーワードで検索してみましょう。クリニックのホームページに、どのような疾患を専門に扱っているか、どのような治療法(特に精神療法)を提供しているかなどが記載されている場合があります。
- かかりつけの内科医や、これまでに受診した医療機関で相談し、適切な専門医を紹介してもらうことも有効です。
- 家族や友人など、身近な人に相談し、良い医療機関を知っているか尋ねてみるのも良いでしょう。
- 診療経験: 身体症状症や心身症の診療経験が豊富な医師がいるかどうかが重要です。ホームページなどで確認できる場合もありますが、電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。
- 治療アプローチ: 精神療法(特に認知行動療法)を中心とした治療を提供しているかどうかも重要なポイントです。薬物療法だけでなく、精神療法に力を入れているクリニックを選ぶことをおすすめします。
- アクセス: 定期的に通院することになるため、自宅や職場からのアクセスが良いかどうかも考慮しましょう。
- 医師との相性: 精神科や心療内科の治療では、医師との信頼関係が非常に重要になります。初診で医師との相性が合わないと感じた場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを受けることも検討して良いでしょう。
- 情報収集:
- 受診時の準備:
- 初診時には、これまでの経過を正確に伝えることが診断に役立ちます。
- 症状について: いつから、どのような身体症状があるのか、症状の具体的な内容、強さ、頻度、変動パターン、症状が出やすい状況などをメモしておきましょう。
- これまでの受診歴: これまでにどこの医療機関を、いつ頃受診したのか、どのような検査を受けたのか、どのような診断を受けたのか、処方された薬の名前や効果などを整理しておきましょう。お薬手帳があれば持参すると良いでしょう。
- 症状に対する考えや感情: 症状について自分がどのように考えているのか、どのような気持ちになるのかを整理しておきましょう。
- 困っていること: 症状によって日常生活や社会生活で具体的にどのようなことに困っているのかを伝えましょう。
- ストレス状況: 現在抱えているストレスについて具体的に伝えられるように準備しておきましょう。
- 信頼できる家族などに付き添ってもらうことも、話をする上での助けになる場合があります。
身体症状症は、一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談することが回復への第一歩です。適切な診断と治療を受けることで、症状による苦痛を軽減し、より充実した生活を送ることが可能になります。
まとめ:身体表現性障害(身体症状症)への理解と回復へ
この記事では、かつて身体表現性障害と呼ばれ、現在は主に身体症状症として理解されている疾患について詳しく解説しました。身体症状症は、**身体的な不調が存在し、それに対して過剰な思考、感情、行動が伴うことで、著しい苦痛や日常生活上の障害を引き起こす精神疾患**です。症状そのものが医学的に説明できるか否かにかかわらず、症状に対する個人の捉え方や反応の仕方が、苦痛の主体となる点がこの疾患の核となります。
DSM-5で診断概念が見直され、身体的な病気の有無よりも、症状に対する認知、情動、行動の偏りに焦点が当てられるようになったことは、この疾患の病態理解が進んだことを示しています。身体症状症は、単なる「気のせい」や精神論で片付けられる問題ではなく、脳機能、心理的な要因、社会的要因、過去の経験などが複雑に絡み合って生じる、医療的なサポートが必要な状態なのです。
現れる身体症状は頭痛、腹痛、めまい、疲労感など多岐にわたりますが、それに加えて「重篤な病気ではないか」という過剰な不安、症状への過度な注意や確認、頻繁な医療機関の受診といった「症状への過剰なとらわれ」こそが、患者さんの苦痛を増大させ、生活を制限してしまいます。
診断にあたっては、まず身体症状の原因となる他の医学的な病気がないかを徹底的に調べる「鑑別診断」が重要です。その上で、精神科医による詳細な問診や評価が行われ、DSM-5の診断基準に基づいて診断が確定されます。
治療の中心は、症状に対する非適応的な思考や行動パターンを修正することを目指す**認知行動療法(CBT)などの精神療法**です。必要に応じて、併存する精神疾患や症状そのものの緩和のために薬物療法が用いられることもあります。そして、治療効果を高め、症状との付き合い方を学ぶ上で、ストレス管理、適度な運動、健康的な生活習慣、感情表現の練習といった**日常生活でのセルフケア**が非常に重要となります。
もし、身体の不調が続き、医療機関で原因が見つからないのに不安や苦痛が強い場合、あるいは症状に対する過剰な心配で日常生活に支障が出ている場合は、一人で抱え込まず、**精神科や心療内科といった専門の医療機関に相談する**ことを強くお勧めします。心身両面からアプローチできる心療内科が適している場合もありますが、精神科でも身体症状症の診療経験のある医師は多くいます。信頼できる医療機関を見つけ、適切な診断と治療を受けることが、苦痛を軽減し、回復への道を歩み始めるための第一歩となります。
身体症状症は、適切な治療とセルフケアによって、症状による苦痛を軽減し、生活の質を改善することが十分可能な疾患です。病気を正しく理解し、希望を失わずに治療に取り組むことが、回復への鍵となります。
—
免責事項: 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、医学的な助言、診断、治療を代替するものではありません。特定の症状や疾患に関するご相談は、必ず医師や専門家にご相談ください。また、記事内容は執筆時点のものであり、情報の完全性や最新性を保証するものではありません。